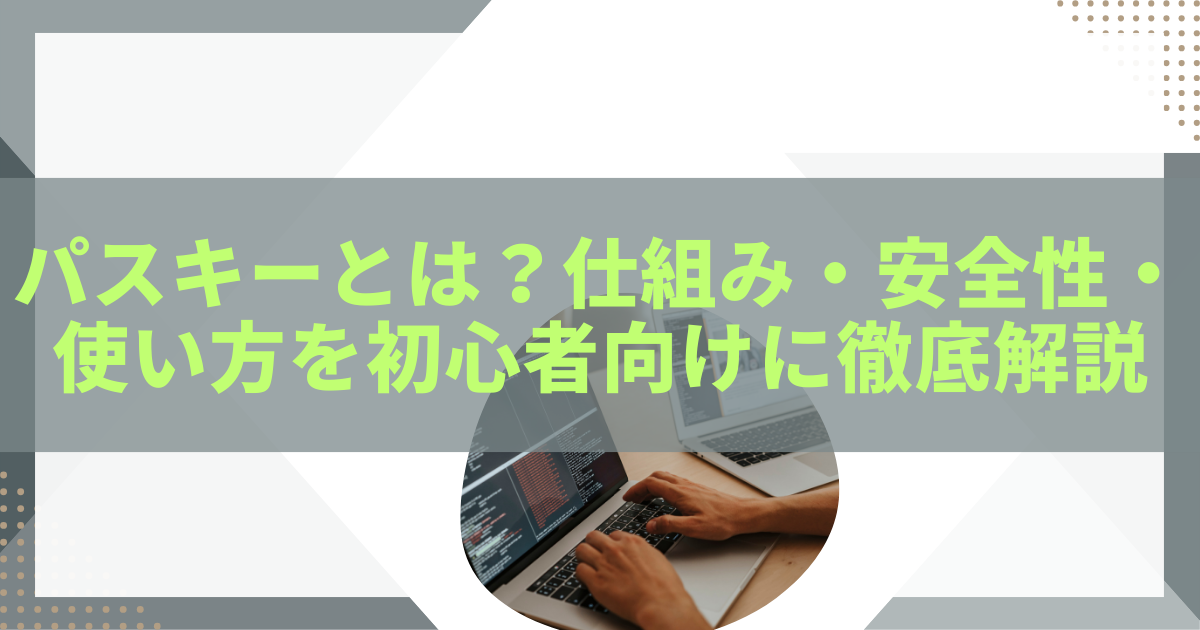
「パスワードを覚えるのが面倒…」「フィッシング詐欺が怖い…」そんな悩みを解決するのが、新しい認証方式「パスキー」です。
パスキーとは、公開鍵暗号方式を利用した仕組みで、パスワードのように覚える必要がなく、生体認証やPINで安全にログインできる方法です。
すでにGoogleやApple、Microsoftといった大手サービスが対応を進めており、主要なOSやブラウザでも利用可能になっています。
この記事では、パスキーの仕組みから安全性、対応デバイスやブラウザ、実際の使い方までを徹底解説します。
「パスキーとは何か?」を理解すれば、あなたのデジタルライフはより安心で快適なものになるはずです。
パスキーとは何か?基本の仕組みをやさしく解説
ここでは、そもそも「パスキーとは何か?」を基礎から解説します。
パスワードとの違いや、パスキーがどのように動作するのかをイメージしやすい形で紹介します。
パスワードとの違いをひとことで説明すると?
パスキーは、従来の「覚える必要があるパスワード」とは異なり、ユーザー自身が意識して文字列を入力する必要がありません。
たとえば、Googleアカウントにログインするとき、パスワードではなくスマホの顔認証や指紋認証で本人確認が完了します。
つまり「パスキー=生体認証やPINなどを使った新しいログイン手段」と理解すると分かりやすいです。
| 認証方式 | 特徴 |
|---|---|
| パスワード | 覚える必要がある。流出のリスクが高い。 |
| パスキー | 覚える必要がない。端末に保存され、生体認証などで利用。 |
公開鍵暗号方式を使った認証の流れ
パスキーの仕組みのカギとなるのが「公開鍵暗号方式」です。
これは「公開鍵」と「秘密鍵」という2つの鍵をペアにして使う技術です。
公開鍵は誰でも見られますが、秘密鍵はユーザーの端末にだけ保存されます。
ログインするときには、秘密鍵で作られた署名を公開鍵で照合することで「正しい本人かどうか」を判定します。
つまり、秘密鍵を知られることがないため、外部から盗まれるリスクが圧倒的に少ないのです。
| 流れ | 説明 |
|---|---|
| 1. 公開鍵の保存 | サービス側がユーザーの公開鍵を記録 |
| 2. ログイン要求 | サービスから「チャレンジ」が送られる |
| 3. 秘密鍵で署名 | 端末内で秘密鍵を使って署名を作成 |
| 4. 公開鍵で検証 | サービス側が署名を公開鍵で検証し、一致すれば認証完了 |
なぜパスキーは安全と言えるのか
ここでは、パスキーが「安全」と評価される理由を整理します。
従来のパスワード方式との比較を通じて、パスキーの強みを確認しましょう。
従来のパスワードが抱えるリスク
パスワードには大きく3つの弱点があります。
まず「使い回しによるリスク」。1つのパスワードが漏れると、他のサービスも突破されやすくなります。
次に「フィッシング詐欺」。ユーザーが誤って偽サイトに入力すれば、簡単に盗まれてしまいます。
最後に「データ漏えい」。企業のサーバーからパスワードが流出すれば、暗号化されていても解析される可能性があります。
つまり、パスワードは「知識」に依存するため攻撃者に狙われやすい仕組みなのです。
| リスクの種類 | 具体例 |
|---|---|
| 使い回し | 同じパスワードで複数のSNSやメールにログイン |
| フィッシング | 本物そっくりの偽サイトで入力を促される |
| データ漏えい | 企業のサーバーからハッシュ化されたパスワードが流出 |
パスキーが防ぐことができる攻撃手法
一方で、パスキーは「秘密鍵を入力する場面が存在しない」ため、そもそも盗まれる余地がありません。
秘密鍵は端末内に安全に保存され、外部に送信されるのは署名データだけです。
さらに、生体認証やPINを組み合わせるため「本人しか使えない」仕組みになっています。
結果として、パスキーはフィッシングや総当たり攻撃といった典型的な攻撃に非常に強いのです。
| 攻撃手法 | パスワード | パスキー |
|---|---|---|
| フィッシング | 偽サイトに入力して盗まれる | 秘密鍵を入力しないため無効 |
| 総当たり攻撃 | 弱いパスワードなら突破可能 | 秘密鍵は複雑で解読不能 |
| データ漏えい | 流出リスクが高い | 公開鍵だけでは突破できない |
パスキーと二要素認証・多要素認証の関係
ここでは、パスキーが従来の二要素認証(2FA)や多要素認証(MFA)とどう違うのかを整理します。
一見まったく異なる仕組みに見えますが、実は共通点もあるのです。
2FAやMFAとの違いを整理する
2FA(二要素認証)は「知っているもの(パスワード)」と「持っているもの(スマホなど)」を組み合わせる方法です。
MFA(多要素認証)はこれをさらに拡張し、複数の認証要素を組み合わせます。
一方、パスキーは「秘密鍵(持っているもの)」と「生体認証やPIN(本人を示すもの)」を組み合わせる仕組みです。
つまり、パスキー自体が2FAやMFAの考え方を内包していると言えます。
| 方式 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 2FA | 2つの異なる要素を組み合わせる | パスワード+SMSコード |
| MFA | 2つ以上の要素を利用 | パスワード+アプリコード+指紋認証 |
| パスキー | 秘密鍵+生体認証を端末内で処理 | 顔認証や指紋で自動ログイン |
パスキーが多要素認証を内包している理由
パスキーでは、認証時に「端末に保存されている秘密鍵」が使われます。
さらに、その秘密鍵を使うために「本人確認」が必要です。
この本人確認は多くの場合、指紋や顔認証といった生体認証です。
結果として、本人の端末と本人の生体情報という二重の仕組みが自然に組み込まれているのです。
ユーザーは複雑な操作を意識することなく、裏側で多要素認証と同等の安全性を得られるのがパスキーの大きな魅力です。
| 認証要素 | パスキーでの実装例 |
|---|---|
| 所有しているもの | 秘密鍵を保存したスマホやPC |
| 本人を示すもの | 指紋認証、顔認証、PIN |
パスキーに対応しているOSとブラウザ一覧
次に、実際にパスキーがどの環境で利用できるのかを見ていきましょう。
2025年現在、主要なOSやブラウザはすでに幅広く対応しています。
Windows・macOS・iOS・Androidの対応状況
パスキーは最新のOSバージョンで標準機能として利用可能です。
各OSの対応状況は以下のとおりです。
| OS | 対応バージョン | 保存場所 |
|---|---|---|
| Windows | 10 / 11 バージョン23H2以降 | Windows Hello |
| macOS | 13 Ventura以降 | iCloudキーチェーン |
| iOS | 16以降 | iCloudキーチェーン |
| Android | 9以降 | Googleパスワードマネージャー |
主要なスマホやPCであれば、ほぼすぐにパスキーを使える環境が整っています。
主要ブラウザ(Chrome・Safari・Firefoxなど)の対応状況
ブラウザもパスキーに対応しているものが増えています。
Chromium系ブラウザ(Chrome、Brave、Opera、Vivaldiなど)は標準対応済みです。
また、SafariもmacOSやiOSの標準ブラウザとして完全対応しています。
Firefoxはバージョン122以降で正式対応しました。
| ブラウザ | 対応状況 |
|---|---|
| Google Chrome | 対応済み(Chromiumベース) |
| Safari | 対応済み(Appleデバイス) |
| Firefox | バージョン122以降で対応 |
| Brave / Opera / Vivaldi | Chromiumベースのため対応済み |
結論として、主要なOSやブラウザではすでにパスキーが利用可能な環境が整っているため、導入を迷う必要はほとんどありません。
パスキーの作成と保存の手順
ここでは、実際にパスキーを作成して保存する方法を解説します。
OSごとに仕組みが異なるため、自分の環境に合わせた方法を確認してみましょう。
Windows HelloやiCloudキーチェーンの使い方
Windowsの場合、パスキーは「Windows Hello」を使って管理されます。
顔認証や指紋認証、PINを設定することで、パスキーの利用が可能になります。
ただしWindowsのパスキーはデバイス間で同期されないため、利用する端末ごとに設定が必要です。
一方、macOSやiOSでは「iCloudキーチェーン」にパスキーが保存されます。
iCloudを利用している場合、自動的にデバイス間で同期されるため、iPhoneやMacのどちらからでも同じパスキーを使えます。
Apple製品ユーザーは一度設定すれば複数端末でシームレスに使えるのが大きな利点です。
| OS | 保存先 | 同期の有無 |
|---|---|---|
| Windows 10/11 | Windows Hello | ×(端末ごと) |
| macOS / iOS | iCloudキーチェーン | ○(Apple IDで同期) |
Googleパスワードマネージャーやサードパーティの選択肢
Androidの場合、デフォルトで「Googleパスワードマネージャー」にパスキーが保存されます。
Googleアカウントに紐付けられているため、複数のAndroid端末間で同期可能です。
さらに、Android 14以降ではサードパーティ製のパスワードマネージャーに保存先を変更できます。
Bitwardenや1Passwordといったサービスを利用することで、OSをまたいだ利用もスムーズになります。
| プラットフォーム | 保存先 | 特徴 |
|---|---|---|
| Android | Googleパスワードマネージャー | 標準で同期可能 |
| Android(14以降) | サードパーティ | 柔軟な保存先の選択が可能 |
自分の利用環境にあわせて、最も管理しやすい保存方法を選ぶことが重要です。
パスワードマネージャーでのパスキー利用方法
ここでは、パスワードマネージャーを使ってパスキーを管理する方法を解説します。
すべてのデバイスでパスキーを統一的に使いたい場合、パスワードマネージャーの利用が便利です。
1Password・Bitwardenなど主要サービスの対応状況
すでに多くのパスワードマネージャーがパスキーに対応しています。
たとえば1Password、Bitwarden、NordPass、Dashlaneなどが代表的です。
これらのサービスを使えば、iPhoneでもAndroidでも同じパスキーを呼び出せます。
異なるOS間でアカウントを横断的に利用する人にとって必須の選択肢といえるでしょう。
| サービス名 | 対応状況 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1Password | 対応済み | 幅広いデバイスで利用可能 |
| Bitwarden | 対応済み | オープンソースで安心感あり |
| NordPass | 対応済み | セキュリティ特化型 |
| Dashlane | 対応済み | UIがシンプルで使いやすい |
複数デバイスでの同期と利用のコツ
パスワードマネージャーを使う最大のメリットは「複数デバイス間での同期」です。
スマホで作成したパスキーを、そのままPCやタブレットでも利用できます。
ただし注意点として、利用するサービスやアプリがパスキーに対応している必要があります。
パスワードマネージャーを導入すれば、どんな環境でも同じログイン体験を得られるのが大きな魅力です。
| 利用環境 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| スマホ+PC | どちらでも同じパスキーを利用可能 | 同期サービスへのログインが必要 |
| 複数OS | 異なるプラットフォームでも利用できる | 非対応アプリでは利用不可 |
実際にパスキーが使えるアプリやサービス
ここでは、すでにパスキーに対応しているアプリやサービスを紹介します。
主要な企業やサービスが導入を進めているため、普段使いのアカウントでも利用できるケースが増えています。
GoogleやAppleなど大手サービスの対応状況
GoogleはGmailやGoogleアカウントへのログインにパスキーを利用できます。
AppleもApple IDやiCloudサービスでパスキーを導入済みです。
そのほかAmazon、Microsoft、Adobeといった大手企業も対応を進めています。
つまり、すでに「毎日使うサービスの多く」がパスキーでログイン可能な時代になっています。
| サービス | 対応状況 |
|---|---|
| 対応済み(アカウント全般) | |
| Apple | 対応済み(Apple ID / iCloud) |
| Microsoft | 対応済み(Outlook / Azureなど) |
| Amazon | 対応済み(アカウントログイン) |
| Adobe | 対応済み(Creative Cloudなど) |
最新の対応アプリを調べる方法
パスキー対応状況は日々変化しており、新しいサービスが次々と導入しています。
最新の情報を調べるには、以下の方法が有効です。
特に「2factorauth」のディレクトリはコミュニティによって継続的に更新されているため信頼性が高いと言えます。
| 調べ方 | 特徴 |
|---|---|
| 1PasswordやHankoのリスト | 主要サービスを中心にまとめている |
| 2factorauth(GitHub) | カテゴリ別で整理され、最新情報が反映される |
| 各サービスの公式ページ | 導入時期や利用条件が正確にわかる |
パスキーはパスワードを完全に置き換えるのか?
ここでは、パスキーが将来的にパスワードを完全に不要にできるのかを考察します。
すでに多くの利点がある一方で、普及には課題も残されています。
普及に向けた課題と制約
第一の課題は「非対応サービスの存在」です。
まだすべてのアプリやWebサイトがパスキーを導入しているわけではありません。
第二の課題は「利用者側の慣れ」。パスワード文化に慣れた人が、新しい方式をすぐに受け入れるのは簡単ではありません。
第三に「アカウント復旧の手順」。端末を紛失した場合などのリカバリーが、ユーザーにとって不安材料になることがあります。
この3つの課題が解決されない限り、完全な移行は難しいと考えられます。
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 非対応サービス | まだ一部のサイトでは利用不可 |
| 利用者の慣れ | パスワード入力に安心感を持つ人も多い |
| アカウント復旧 | 紛失や盗難時の対応が課題 |
今後の展望とセキュリティの未来
とはいえ、主要な企業がパスキー導入を推進しているため、普及は時間の問題です。
特にGoogleやAppleのような「ID基盤」となるサービスで標準化されたことで、利用者の意識も自然に変わっていくでしょう。
さらに、パスキーはセキュリティだけでなく「快適さ」も提供します。
生体認証で一瞬でログインできるため、パスワードを覚える必要がなくなるのです。
将来的には、パスキーが「当たり前の認証方式」となり、パスワードは過去の遺物になる可能性が高いといえるでしょう。
| 観点 | パスキーの優位性 |
|---|---|
| 安全性 | フィッシングや総当たり攻撃に強い |
| 利便性 | 生体認証で瞬時にログイン |
| 将来性 | 大手企業が採用を推進 |
まとめ:パスキーで得られる安心と快適さ
ここまで、パスキーの仕組みから安全性、対応環境、使い方までを解説してきました。
最後に、今から利用を始めるメリットと、これからの認証方式との付き合い方を整理しておきましょう。
今から利用を始めるメリット
パスキーの最大のメリットは「覚える必要がない安全な認証方式」であることです。
生体認証やPINを使うため、パスワードのように漏えいリスクが少なく、ログインもスムーズです。
さらに、主要なOSやブラウザがすでに対応済みなので、特別な設定なしで利用を始められるケースが増えています。
今からパスキーを導入すれば「安全性」と「快適さ」を同時に手に入れられるのです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| セキュリティ | フィッシングや総当たり攻撃に強い |
| 利便性 | パスワード入力が不要でスムーズ |
| 対応環境 | 主要OS・ブラウザがすでに利用可能 |
これからの認証方式との付き合い方
パスキーは確かに便利ですが、すべてのサービスが完全対応するまでには時間がかかります。
そのため当面は「パスキーが使えるサービスはパスキー、使えないサービスはパスワード」というハイブリッド運用が現実的です。
ただし、GoogleやAppleといった主要サービスが積極的に導入を進めていることから、移行は確実に加速していきます。
「まずはメインのアカウントから導入してみる」ことが最も効果的な第一歩です。
これからの時代、パスキーを活用できるかどうかが「セキュリティリテラシーの新基準」となるでしょう。
| ステップ | 実践内容 |
|---|---|
| 1 | GoogleやApple IDなど主要アカウントでパスキーを設定 |
| 2 | 対応しているアプリやサービスを順次切り替え |
| 3 | 非対応サービスはパスワードマネージャーで安全に管理 |